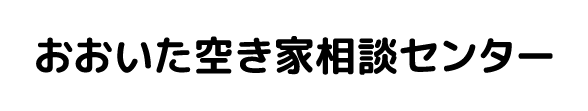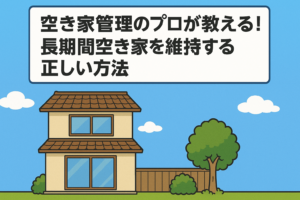空き家の固定資産税が6倍に?特定空家認定を避けるための対策法
はじめに
「空き家を放置していたら、急に固定資産税の通知額が大幅に増えていた」—このような事態に直面する空き家所有者が全国で増加しています。その背景にあるのが「空家等対策の推進に関する特別措置法」による「特定空家等」の認定制度です。特定空家等に認定されると、それまで適用されていた住宅用地特例が除外され、固定資産税が最大6倍に跳ね上がる可能性があります。本コラムでは、特定空家等認定の仕組みと、認定を避けるための具体的な対策について詳しく解説します。
特定空家等制度の基本知識
空家等対策特別措置法とは
制定の背景 全国で増加する管理不全な空き家による地域への悪影響を防止するため、2014年に制定され、2015年5月から全面施行されました。2023年12月には法改正が行われ、予防的措置の強化が図られています。
法律の目的
- 適切な管理が行われていない空家等の活用促進
- 地域住民の生命・身体・財産の保護
- 生活環境の保全
- 空家等の利活用の促進
特定空家等の定義
法律では、以下の状態にある空家等を「特定空家等」として定義しています:
1. 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 建築物が著しく傾斜している
- 屋根、外壁等が脱落・飛散のおそれがある
- 擁壁が老朽化し危険な状態
2. 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 汚物の放置により臭気が発生
- 害虫・害獣が大量発生
- 建材にアスベストが露出
3. 適切な管理が行われず著しく景観を損なっている状態
- 窓ガラスの破損を放置
- 立木・雑草が繁茂し景観を阻害
- 外壁の汚損・破損が著しい
4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態
- 不法投棄を誘発している
- 犯罪の温床となるおそれ
- 野良猫・野良犬の住み着き
住宅用地特例と税額への影響
住宅用地特例の仕組み
小規模住宅用地(200㎡以下の部分)
- 課税標準額:固定資産税評価額の1/6
- 都市計画税:固定資産税評価額の1/3
一般住宅用地(200㎡超の部分)
- 課税標準額:固定資産税評価額の1/3
- 都市計画税:固定資産税評価額の2/3
特定空家等認定による税額増加の具体例
ケース1:土地200㎡、評価額1,000万円の場合
認定前(住宅用地特例適用)
- 固定資産税:1,000万円 × 1/6 × 1.4% = 約2.3万円
- 都市計画税:1,000万円 × 1/3 × 0.3% = 約1.0万円
- 合計:約3.3万円/年
認定後(特例除外)
- 固定資産税:1,000万円 × 1.4% = 14.0万円
- 都市計画税:1,000万円 × 0.3% = 3.0万円
- 合計:17.0万円/年
年間増加額:約13.7万円(約5.2倍の増加)
ケース2:土地300㎡、評価額1,500万円の場合
認定前
- 固定資産税:約4.8万円/年
- 都市計画税:約2.0万円/年
- 合計:約6.8万円/年
認定後
- 固定資産税:21.0万円/年
- 都市計画税:4.5万円/年
- 合計:25.5万円/年
年間増加額:約18.7万円(約3.8倍の増加)
特定空家等認定の手続きフロー
第1段階:現地調査・所有者特定
行政による実態調査 市町村職員による現地調査が実施され、建物・敷地の状況が詳細に記録されます。
所有者調査 固定資産税台帳や登記簿謄本により所有者が特定され、連絡先の確認が行われます。
第2段階:助言・指導
助言・指導の実施 特定空家等の状態にあると判断された場合、まず所有者に対して助言・指導が行われます。この段階では法的強制力はありません。
改善期限の設定 通常30日から90日程度の改善期限が設定され、具体的な改善内容が示されます。
第3段階:勧告
勧告の実施 助言・指導に従わない場合、勧告が行われます。この段階で住宅用地特例の対象から除外されます。
勧告書の内容
- 改善すべき具体的事項
- 改善期限(通常30日以上)
- 勧告に従わない場合の措置予告
第4段階:命令
命令の実施 勧告にも従わない場合、命令が発せられます。命令違反者には50万円以下の過料が科される可能性があります。
第5段階:行政代執行
代執行の実施 命令にも従わない場合、行政が強制的に除却等の措置を行い、費用を所有者に請求します。
特定空家等認定を避けるための対策
基本的な管理の徹底
定期的な見回り・点検 月1回以上の現地確認を行い、建物・敷地の状況を把握します。
点検チェックポイント
- 屋根・外壁の破損状況
- 窓ガラス・ドアの破損
- 雑草・立木の繁茂状況
- ゴミの不法投棄
- 害虫・害獣の発生
適切な清掃・整備
- 敷地内の清掃
- 雑草除去(年3回以上推奨)
- 不要物の撤去
- 郵便受けの整理
建物の最低限の維持管理
安全性の確保
- 破損箇所の応急修繕
- 危険箇所の立入禁止措置
- 飛散のおそれがある部材の固定・撤去
防犯対策
- 全ての扉・窓の施錠
- 侵入防止措置(板張り等)
- 近隣住民への連絡先提示
衛生環境の維持
- 害虫・害獣の駆除
- 異臭の発生源除去
- 排水設備の管理
近隣住民との関係維持
コミュニケーションの重要性 近隣住民からの苦情は、行政による調査のきっかけとなることが多いため、良好な関係維持が重要です。
対応のポイント
- 管理責任者の連絡先明示
- 定期管理のスケジュール共有
- 問題発生時の迅速な対応
- 改善計画の説明
専門家による建物診断の活用
建築士による診断 建物の安全性について専門家の客観的な判断を得ることで、適切な対策を講じることができます。
診断項目
- 構造の安全性評価
- 修繕優先度の判定
- 改善方法の提案
- 概算費用の算出
行政指導を受けた場合の対応
助言・指導段階での対応
迅速な現状確認 指導内容と現地の状況を照合し、改善が必要な箇所を正確に把握します。
改善計画の策定
- 改善項目の優先順位付け
- 具体的な実施方法の検討
- 必要な費用の概算
- 実施スケジュールの作成
行政との協議 改善計画について行政担当者と協議し、実現可能な期限での合意を目指します。
勧告段階での緊急対応
**法的影響
投稿者プロフィール
最新の投稿
 コラム2025年8月6日空き家相続の落とし穴 - 相続登記義務化で知っておくべきポイント
コラム2025年8月6日空き家相続の落とし穴 - 相続登記義務化で知っておくべきポイント コラム2025年8月5日空き家の固定資産税が6倍に?特定空家認定を避けるための対策法
コラム2025年8月5日空き家の固定資産税が6倍に?特定空家認定を避けるための対策法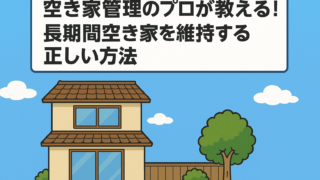 コラム2025年8月4日空き家管理のプロが教える!長期間空き家を維持する正しい方法
コラム2025年8月4日空き家管理のプロが教える!長期間空き家を維持する正しい方法 コラム2025年8月3日相続した実家が空き家に…まず何をすべき?専門家が教える初動対応
コラム2025年8月3日相続した実家が空き家に…まず何をすべき?専門家が教える初動対応